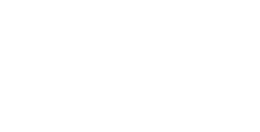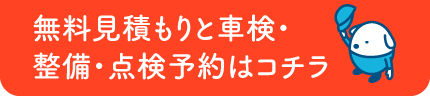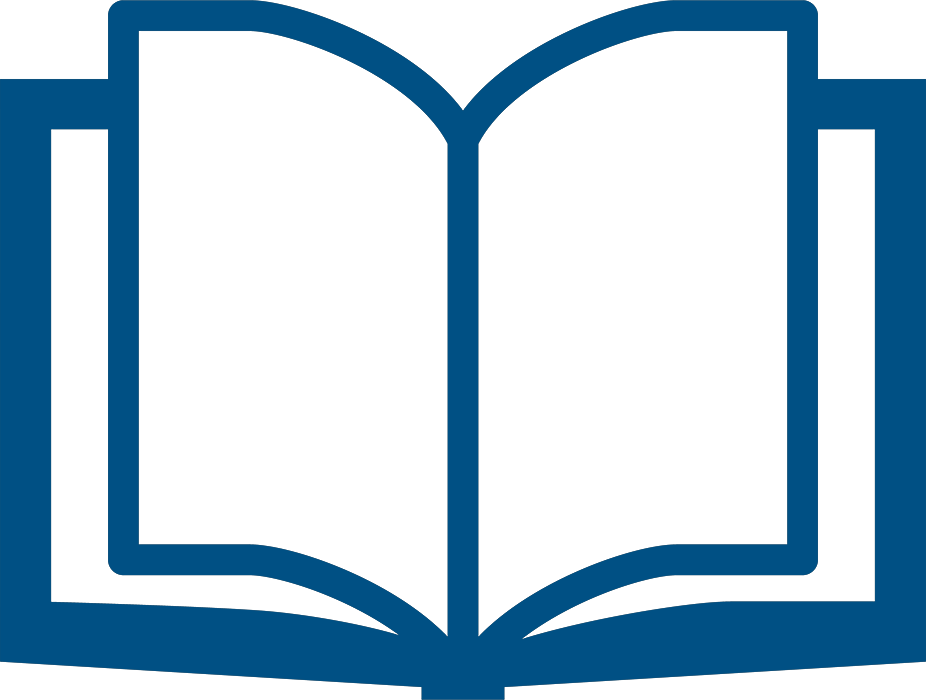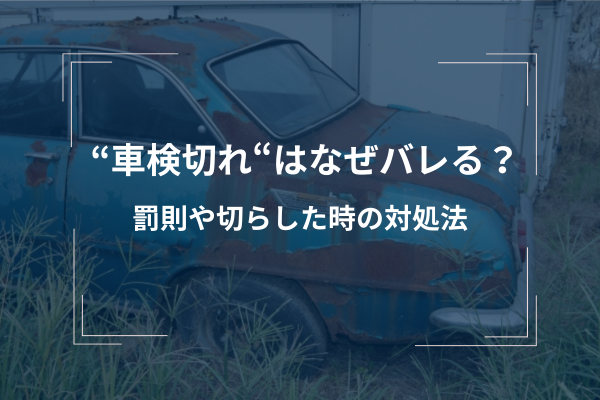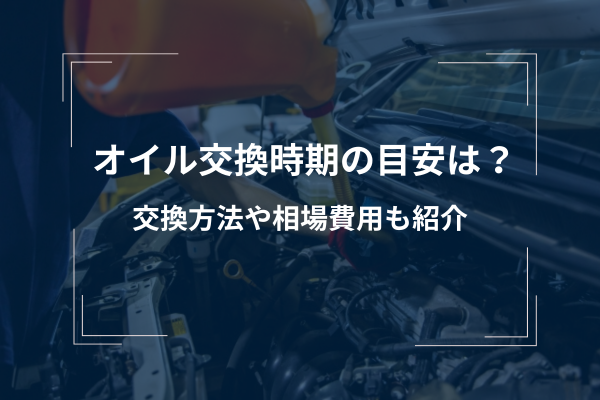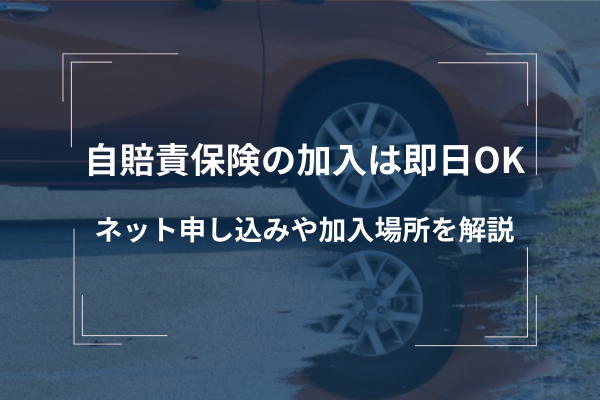事業用の車を取得した場合、購入代金は減価償却によって経費計上します。
これは、新車・中古車問わず、税制上のルールとして定められている事柄です。
しかし、新車と中古車では減価償却に異なる点もあるので注意しましょう。
今回は中古車の減価償却について解説し、注意点も取り上げています。
事業用車両の取得を考えている事業者の方は、参考にしてください。
目次
減価償却とは
減価償却とは事業用に購入した物品の代金を、数年に分けて経費計上する仕組みです。
消耗品ではない設備や機器などは、時間をかけて少しずつその価値が減っていくものとし、所定の耐用年数に分けて経費計上します。
耐用年数は物品ごとに定められており、金額を自由に決められるわけではありません。
減価償却の対象となるのは、一式あたりの価格が10万円以上で、経年によって価値が消費される固定資産です。
よって、業務用のパソコンや複合機、車両を購入した場合などは、減価償却の対象となります。
ただし、年数が経過しても価値が消費されない・されにくい、土地や骨董品などは対象外です。
廃車してもお金が戻ってくるの?還付金を受け取る条件を徹底解説
中古車で減価償却する方法は2種類
中古車を減価償却する場合、定額法と定率法の2種類の方法が存在します。
定額法
定額法は、物品の価値が毎年均等に価値が下がるものとし、購入代金を耐用年数で割った金額を毎年計上します。なお、車の購入代金を減価償却する場合は1年ごとではなく、1年分を12分割してひと月ごとに計上します。
毎年・毎年の償却費が一定で分かりやすく、計算が容易な方法です。
たとえば、120万円で購入した中古車の耐用年数が4年(48か月)であったなら、年間の減価償却費は30万円、毎月25,000円を計上します。
この方法では、年数が経過して物品の価値が下がっても、一定の償却費が計上され続けます。
そのため、年数が経つにつれて、物品の価値に対する償却費の比率が高くなるのも特徴です。
定率法
定率法は物品の残りの価値に対して、一定割合の金額を計上する方法です。
償却費は償却率によって求められ、経年によって物品の価値が下がっても、一定割合の金額を計上します。
なお、償却率は耐用年数ごとに決められています。
たとえば、150万円で購入した耐用年数4年の中古車で、定率法を使うケースで計算してみましょう。この場合、償却率は0.625です。
まず、1年目は150万円×0.625=937,500円が償却費となり、これを月割りにして毎月計上します。
2年目の償却費は、1年目に計上した分を差し引いた残りの額に対して償却率をかけます。
(150万円-937,500円)×0.625=351,562円
償却費は351,562円となり、これを月割りにして毎月計上します。
このように定率法では、購入直後の資産価値が高い状態にあるときに償却費が多くなり、経年によって価値が下がるにつれて償却費も減るのが特徴です。
新車と中古車の減価償却の違い
新車と中古車では、耐用年数にも違いがあります。
事業で使う車の減価償却では、定額法・定率法だけで償却費が決まるわけではないので注意しましょう。
新車の耐用年数
新車の耐用年数は、車両の用途と車種によって変化します。
一般事業用の車であれば、普通自動車は6年、軽自動車は4年が耐用年数です。
|
一般事業用の新車耐用年数 |
|
|
総排気量0.66リットル以下の小型車 |
4年 |
|
ダンプ式の貨物自動車 |
4年 |
|
その他の貨物自動車 |
5年 |
|
報道通信用の車両 |
5年 |
|
その他の自動車(普通自動車) |
6年 |
|
2輪・3輪自動車 |
3年 |
運送事業や貸自動車業など、車を使うことを前提とした事業の車であれば、耐用年数は以下のようになります。
|
運送事業用・貸自動車業用・自動車教習常用の新車耐用年数 |
|
|
総排気量0.66リットル以下の小型車(貨物自動車は積載量2トン以下、その他は総排気量2リットル以下) |
3年 |
|
総排気量3リットル以上の大型乗用車 |
5年 |
|
その他の自動車 |
4年 |
|
乗合自動車 |
5年 |
|
その他の自動車(普通自動車) |
6年 |
中古車の耐用年数
中古車の場合、新車の状態から経過した年数があるため、法定耐用年数をそのまま適用できません。
この場合、簡便法という計算式によって耐用年数の計算が可能です。
計算式は「法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2」ですが、法定耐用年数が過ぎている場合は「法定耐用年数×0.2」で計算します。また、1年未満の端数は切り捨てとなり、2年未満になる場合は2年とします。
たとえば、新車登録から2年経っている普通自動車なら「6年-2年+0.4年=4.4年」となり、耐用年数は端数を切り捨てた4年です。
もし、6年の耐用年数を過ぎた中古の普通自動車なら「6年×0.2=1.2年」となり、2年未満となるので耐用年数は2年です。
廃車するとお金がもらえる?自動車税の還付金の受け取り方法と注意点
中古車で減価償却する時のポイント
車の減価償却におけるポイントは、カーリースの場合は計上方法が異なる点や、ローン購入時の減価償却は返済額とは別である点などがあります。
また、事業用の車をマイカーと兼用するなら、私的な使用分に応じて減価償却費は下がるので注意しましょう。
カーリースなら全額経費に計上できる
事業用車両の購入ではなくカーリースならば、固定資産として車を所有している状態に該当しないため、減価償却そのものが不要です。
毎月のリース代をそのまま経費として全額計上でき、わずらわしい償却費の計算は必要ありません。
またカーリースの月額費用には、車の維持費として発生する自動車税金や自賠責保険料、車検代・メンテナンス代なども含まれているのが一般的です。
そして、税金や保険料の納付手続きは、車の所有者であるリース会社が対応します。
カーリースなら車にかかる経費処理を簡略化でき、税金や保険料を納める手間から解放されるメリットがあります。
ローンで購入した場合も減価償却は可能
ローンを組んで中古車を購入した場合も、購入代金を毎月減価償却します。
ただし、毎月の償却費は、金融機関に毎月支払うローン返済額を指すわけではありません。
定額法または定率法によって、中古車の購入にかかった代金を減価償却します。
そのため、毎月のローン返済額と償却費は、同じ金額にはなりません。
なお、ローンによって発生する利息分は、支払利息として償却費とは別に計上します。
マイカーとして利用すると減価償却費が下がる
事業用に購入した車を、マイカーとして兼用する場合もあるでしょう。
この場合、プライベート利用に相当する金額分は個人の負担とし、事業で使用した部分のみが経費となるため、減価償却する金額が下がります。
マイカーを兼ねている車の代金から、事業用にあたる割合分を経費として扱う方法を按分といいます。
按分する割合は事業者が決められますが、税務調査で指摘される可能性のあるポイントです。
たとえば、ほとんどマイカーとして使っている車を、80%の割合で事業用の経費にすると、使用実態と会計処理に乖離が生じます。
計上額を事業用と私用とで按分するなら、客観的に見ても妥当であると判断してもらえる割合にしましょう。
4ナンバー車の車検費用は高い?安い?税金や保険料の違いを解説
まとめ
事業用の車を取得した場合、購入時点で代金をまとめて経費計上するのではなく、定められた耐用年数と償却率で分けて減価償却します。
事業用の車を購入したのであれば、新車・中古車を問わず、このような処理になるので覚えておきましょう。
中古車の減価償却には定額法と定率法の2種類があり、耐用年数は簡便法によって計算します。
なお、購入ではなくカーリースならば、リース代を毎月経費として計上し、減価償却はしません。
ローンで購入した場合は、返済額を経費として計上するのではなく、車の代金と耐用年数・償却率から求めた償却費を毎月計上します。
また、事業用の車をマイカーとしても使うなら、私的な使用にあたる分の金額を差し引いた残りを減価償却するので、減価償却費は下がります。