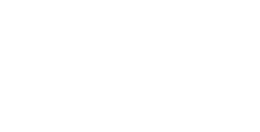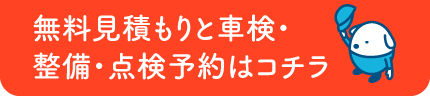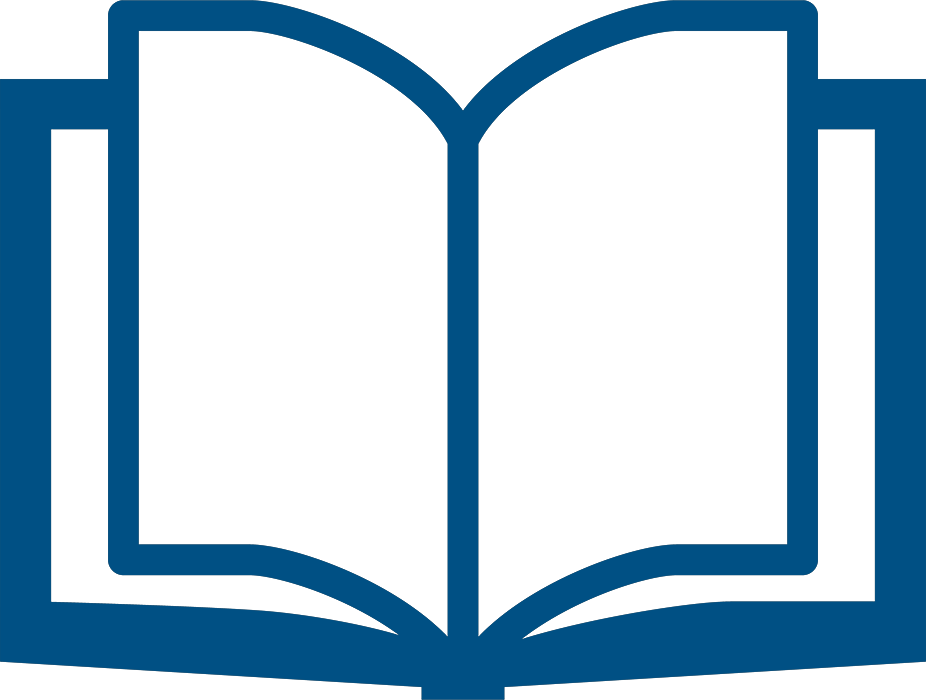『そのヘッドライト、車検の審査基準満たしていますか?』
車検費用を少しでも安く抑えるためにユーザー車検を行う方も多いかと思いますが、2024年8月よりヘッドライトの審査基準が変わったことをご存じでしょうか?
この変更により、ヘッドライトの審査に引っかかってしまい車検が通らず、安くおさえようとしたユーザー車検に、結局は追加費用がかかってしまったというケースもあります。
つまり、車検の前に詳しく知っておかないと損をしてしまうこともあるのです。そこで今回は、車検のヘッドライト審査基準の変更内容や、どのようにすると安心して車検に合格するのかを具体的に見ていきます。
目次
2024年8月からヘッドライトの車検項目が変更

検査基準は2015年9月1日に改訂され、その後2018年からロービームでの検査が始まりました。
従来はハイビーム検査に加えてロービーム検査も「原則」とされていましたが、「やむを得ない場合にはハイビームのみで可」という例外規定が設けられていました。
しかし、2024年8月からこの例外規定が廃止され、すべての車両に対してロービームでの検査が義務付けられることになりました。
※ただし、一部の地域では最長で2年間の猶予が認められています。
【地域別】検査項目の移行時期
————————————–
2024年8月から完全移行 ⇨ 北海道・東北・北陸信越・中国の陸運局
2026年8月1日まで最長2年延期 ⇨ 関東・中部・近畿・四国・九州・沖縄の陸運局
————————————–
延期の理由について、自動車技術総合機構は「対象となる車両の数が多く、さまざまな事情から地域によってはまだ十分な周知が行き届いていないため、猶予期間を2年延長する」と説明しています。
延期の対象地域については、各地域の移行状況を考慮しながら、2026年8月1日までに段階的に移行が進められることが決まっています。
ヘッドライトの保安基準は大きく3つ

①光度や色
ヘッドライトの明るさは規定以上の数値がなければならず、その色もこれまでの黄色から白色に変更となりました。
今後は白色ライトを選ぶ必要がありますが、単位となる「ケルビン」数値が高いものは青白くなり、低いものは黄色くなるため、3,500~6,000ケルビンあるライトをおすすめします。
また、最も明るい部分が1mと10mで違いがない光量をこれまでの審査基準としていましたが、1つのライトに対し、6,400カンデラ以上の明るさが必要となりました。
これまでのようにライトやバルブ自体の明るさを測定するのではなく、リフレクターなどに反射した際の光の明るさを測定するようになったことも注目すべき変更点です。
②光軸など照射範囲
ハイビームにおける旧基準では照らす方向が合っていれば車検には通っていましたが、ロービームにおける新基準ではこれが変更となりました。
対向車の視界を遮らないように、右側上部への照射を避けることはもちろん、歩道側である左側の視認性を上げる工夫が求められています。
このような照射範囲と、逆に光を遮る範囲の境界線をカットオフラインと呼び、このラインとエルボー点と呼ばれる測定基準が前方10mを照らした際に規定位置にあれば車検に通ることになりました。
光軸は、車のボディに強い衝撃が加えられたりバルブ交換でもズレてしまうことがあるので、車検予約の前など必ず自分で点検するか無料点検に出すようにしましょう。
③点灯状態とヘッドライトカバーの状態
車検の際はヘッドライトの正確な光度をよく確認する必要があります。そのため、バルブが切れていて点灯しないといった場合は交換が必要となります。
また、ヘッドライトカバーが割れていたり、大きなキズがあるといった場合も、割れやキズから光が漏れてしまうこともあるため取り換えが必要となります。
このような点灯状態やヘッドライトカバーの状態では車検に通らなくなってしまうことはもちろん、事故を引き起こす原因となってしまうことも考えられます。
車検予約前に必ずチェックし、問題がある場合は必ず修理するように日ごろから心がけるようにしましょう。
車検落ちするヘッドライトの特徴
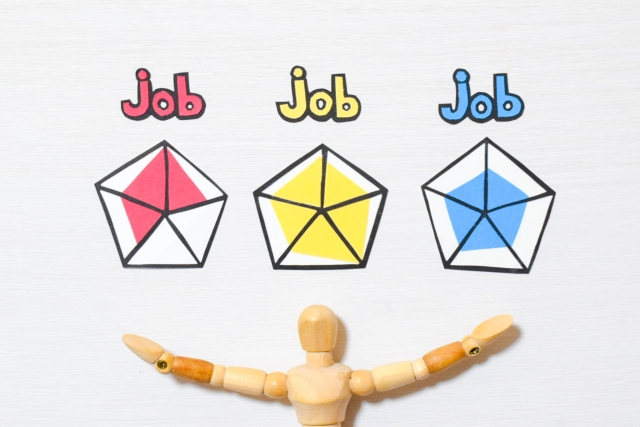
レンズの黄ばみ・曇り
ヘッドライトのレンズが黄ばんだり、曇ったりしていると光量が正常時より落ちてしまうため、運転上危険です。そして運転に支障をきたすことは車検にも通らないということにつながります。
旧基準と異なり、新基準では前述のようにヘッドライトの測定対象がハイビームからロービームへ変更となりました。
黄ばみや曇りによる光量不足は、ロービームの場合、ハイビームに比べはっきりと影響されてしまうため、このような場合は交換したり磨くなどして事前に対処しましょう。
社外品のバルブを使用
純正ではなく、自分で社外品のバルブを交換してしまった場合、このような車は車検に通らなくなってしまいます。
これは、社外品のバルブであると、取り付け車種のリフレクターにうまく合わないため、光が反射してしまい、照射ができなくなってしまうからです。
さらに、hosi 明るさも不足するため、車検合格はもとより事故の危険性も高まるためやめた方がよいでしょう。また、カットオフラインも明確にならないため、こうした点でも危険と言えます。
ライトの種類はどれがいい?

ハロゲン(白熱電球)
後述するバイキセノンが普及するまで、車のヘッドライトはハロゲンが一般的でした。
ライトの色は黄色といった暖色系で、対向車にやさしいという点ではメリットですが、光量はバイキセノンやLEDには劣るためデメリットとも言えます。
また、他のライトに比べて寿命が短く、消耗品となるので、取替の頻度は多くなります。ただ、価格に関しては他のライトに比べて安く、部品や工場整備士による工賃合わせて1,000円から5,000円が価格相場となっています。
バイキセノン(HID・ディスチャージランプ)
ハロゲンと比較すると寿命が長いため、交換頻度は少なくなります。また、ハロゲンよりも少ない発熱で済むため、こうした点もメリットと言えるでしょう。
しかし、バイキセノンのライト交換の場合、部品と工賃は12,000から20,000円ほどが価格相場となり、ハロゲンよりも高くなります。
これはハロゲンより交換が難しいためであり、車種によってはヘッドライト自体の脱着も必要となるため、こうした場合はさらに2,000円ほど上乗せとなってしまいます。
LED
LEDは今から10年ほど前から普及しだした新しいタイプで、発光ダイオードを使用したライトになります。他のライトに比べ圧倒的に長い寿命と少ない消費電力がメリットと言えます。
特に寿命は新車から廃車するまで無交換で済むほどです。
また、点灯速度が速いため、スイッチオンと同時に最大光量を得られる点も魅力と言えるでしょう。価格はバイキセノンよりも低価格で、部品工賃合わせて10,000円から20,000円程度となっています。
損しない為にも車の定期点検が大事
いかがでしたか。最後にポイントを整理すると
- 車検におけるヘッドライトの審査基準が変更になり、一部地域ではロービームの検査が義務化
- 新しい基準ではエルボー点が正しい場所にあるかが重要となるため、衝撃などでズレが生じないよう日頃からチェックが必要
- 黄ばみや曇りそしてヘッドライトカバーの割れなどは光量に影響を与えるため定期的な見直しが必要
などとなります。
車検はなるべく安くおさえたいものです。これまで見てきたようにヘッドライトの審査基準が変わったため、追加費用がかからないためにも車検予約前には必ず基準を満たしているかどうか点検するようにしましょう。
車検館では車の車検だけでなく、定期点検も承っておりますのでこの機会に見直しが必要と感じた方はぜひ一度お越しください。