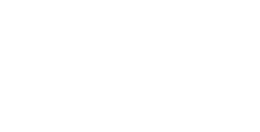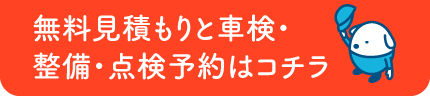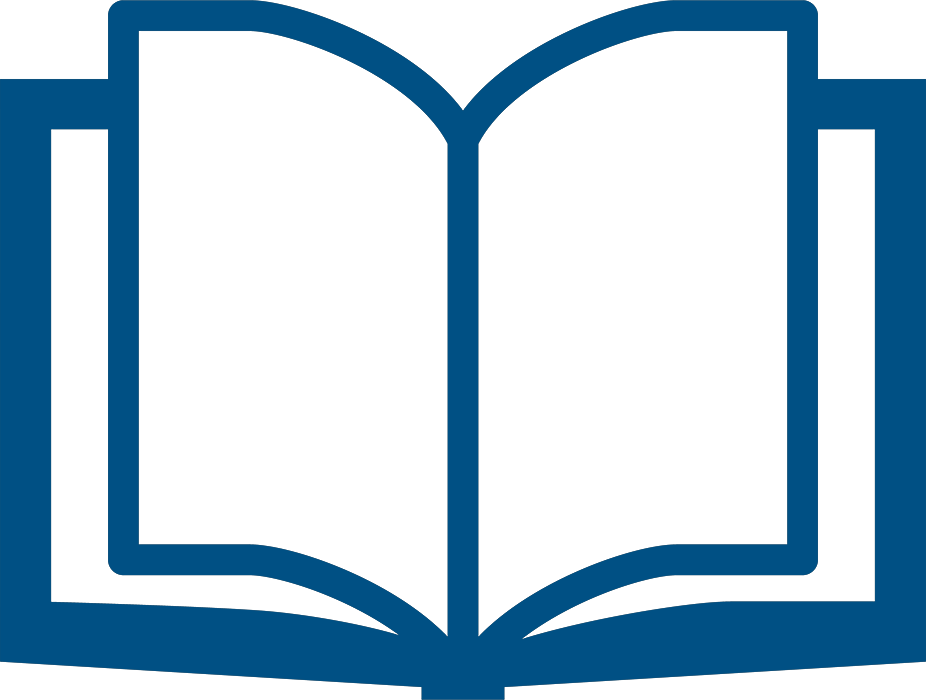車を運転中に突然起こると困るのがバッテリー上がりです。
- 「バッテリーってどうなると上がってしまうのだろう?」
- 「何をすればバッテリー上がりは予防できるの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いことでしょう。
バッテリー上がりは、車が運転できなくなることで身動きがとれなくなってしまうため、場所によっては事故にもつながりかねず危険です。
そこでこの記事では、バッテリー上がりの原因や予防、対処法などについて具体的に解説していきます。
目次
バッテリー上がった時の症状
車の不具合には様々な要因が考えられますが、それがバッテリー上がりによるものか知るには何を確認すべきなのでしょうか?
次に挙げる3つのことがポイントとなります。
エンジンがかからない
バッテリー上がりを確認する際は、まずエンジンがかかるかどうかを確認しましょう。キーを回す、あるいはエンジンボタンを押してもかかりにくい場合、バッテリー上がりやその前兆が疑われます。
しかし、エンジンがかからないトラブルとしてはガス欠も考えられます。
ガス欠は燃料をすべて使い切ってしまった状態を指し、セルモーターは作動するものの、燃料が供給されないのでエンジンがかからなくなってしまいます。
そのため、次に挙げるセルモーターの確認も重要です。
セルモーターが回らない
車が正常な場合、エンジンをかけるとセルモーターの音がキュルキュルと鳴ります。
しかし、セルモーターの回転音が聞こえない場合、もしくはわずかの時間しか聞こえない、回転音が弱いといった場合はバッテリー上がりが考えられます。
バッテリーは前述のとおり、車の様々なパーツに電力を供給しています。セルモーター音ではバッテリー上がりが判断しづらい場合、次に挙げる電装品の確認も行ないましょう。
室内灯や表示ライトがつかない
バッテリーは車の各パーツに電力を供給しているため、室内灯や表示ライト、パワーウインドウ、カーオーディオ、カーナビ、運転席にあるメーター類といった車内にあるすべての電装品が動かなくなります。
また、バッテリーが完全に上がってしまうと、リモコンキーからドアの開閉ができなくなってしまうため、キーシリンダーに手動で鍵を差し込こまなければなりません。
バッテリーが上がったときの対処法5選
では、実際にバッテリーが上がってしまったときは、どのように対処したらよいのでしょうか?その方法について具体的に解説していきます。
①ジャンピングスタートでエンジンをつける
他の車から一時的に電気を分けてもらい、エンジンを始動させることをジャンピングスタートと呼びます。
ジャンピングスタートにはブースターケーブルという専用コードが必要です。
つなぎ方は赤のケーブルを自車と救援車のバッテリーのプラス端子につなぎ、黒のケーブルをそれぞれのマイナス端子につなぎ、エンジンをかけてしばらく待つようにします。
②ジャンプスターターを用いる

ジャンプスターターとは、バッテリー上がりの車のエンジンを動かすための、モバイルバッテリーのことです。
前述のジャンピングスタートには救援車が必要ですが、ジャンプスターターはこの器具だけでエンジンを始動されることができます。
③バッテリーを充電する
カー用品店などで販売されているバッテリー専用充電器は、エンジンをかけずに充電できます。
バッテリー専用充電器は、DC12Vが乗用車使用として一般的ですが、バイクやトラックなどにも使用できるマルチタイプも販売されています。
④バッテリーを交換する
バッテリー上がりの原因が寿命によるものだった場合、早めにバッテリーそのものを交換するようにしましょう。
まだ自走できる場合は、カー用品店やガソリンスタンド、修理工場などに依頼するとよいでしょう。
⑤ロードサービスを呼ぶ
自分でバッテリー充電ができず救援車もない場合は、JAFや保険会社のロードサービスに連絡しましょう。
ロードサービスは、ほとんどの自動車任意保険についており、加入するだけで利用することができます。
バッテリーは自然回復しない
バッテリー上がりが一度でもあると、自然回復することはありません。バッテリー上がりが生じた場合、できるだけ早く新しいバッテリーに交換しましょう。
バッテリーが上がった車をそのままの状態にしておくと、運転席にあるメーター類、ヘッドライト、室内灯などが使用不可能になってしまいます。
さらに、リモコンキーも使用できなくなってしまい、車内に入れなくなります。
バッテリー上がりの車の放置はバッテリー交換代だけでなく、余計な修繕費を生んでしまうため、早めに取り替えるようにしましょう。
バッテリー上がりの前兆は?こんな症状に注意
バッテリー上がりの前兆は以下のようなものがあります。
①エンジンがかけにくい
②走っている時と止まっている時で車のライトの明るさが大きく異なる
③パワーウィンドウ(車の窓)の開閉が遅い
④アイドリングストップすることがなくなった
以上のような症状を放置してしまうとバッテリー上がりを起こしてしまう可能性があるため早急の対応が必要です。
バッテリー上がりではない似た症状の可能性も?
バッテリー上がりのような症状でありながら、実はバッテリー上がりではないとケースもあります。
こうした不具合はすぐに解決できる場合もあるため、以下に挙げる症状が起きていないか確認するようにしましょう。
ガス欠
車の燃料であるガソリンがなければ、当然ながらエンジンは動きません。
このような際、近くにガソリンスタンドがあればガソリン携行缶を借りるなどして給油するか、ガソリンスタンドが見当たらない場合はJAFなどのロードサービスを利用してレッカーしてもらうようにしましょう。
このようにガス欠は危険ですので、ガソリンランプが点灯する前に、給油するよう普段から心がけましょう。
燃料ポンプの故障
「セルモーターはキュルキュルと音を立ててきちんと回っている」また「ガソリンはしっかり入っている」そんな場合でもエンジンがかからず、バッテリー上がりと判断してしまう場合もあります。
しかし、燃料ポンプが故障し、正常にガソリンが供給されていなければエンジンはかかりません。そのため、燃料ポンプも必ず確認するようにしましょう。
セルモーターの故障
バッテリー上がりは、バッテリーにセルモーターを動かすだけの電気量が蓄積されていない状態を指しますが、逆にバッテリーは正常でセルモーターが故障していても、エンジンがかからないという同様の症状は起きます。
このような際は、電装品がきちんと動作するかどうかで判断するとよいでしょう。
ギアの入れ間違い
オートマティック車の場合、パーキングの位置にシフトレバーが入っていなければエンジンがかからないようにできています。
ギアの入れ間違いに気づかず、エンジンがかからずにバッテリー上がりかもと思ってしまう人は意外と多いようです。
エンジンをかけるときはシフトレバーがパーキングの位置にあるかどうかをしっかり確認しましょう。
オルタネーターの故障

オルタネーターとは、自動車に備えられた発電機のことを指します。
オルタネーターは、エンジンの動力を使って発電しバッテリーを充電してくれるため、非常に重要な役割を担っています。
このオルタネーターが故障してしまうと発電がされず、バッテリーに充電がされないことになるため、バッテリー上がりが起きてしまうのです。
ヒューズが切れている

ヒューズは電気回路に何かしらの原因で電流が流れ過ぎてしまった際に、電気回路を遮り電流を止め、電装品や回路を溶解や発火から守ってくれます。
つまり、電流が流れ過ぎてしまうとヒューズが切れてしまい、エンジンをかけるための電気が流れなくなります。そして結果的にエンジンがかからなくなってしまうのです。
電気自動車・ハイブリッドカーのバッテリーが上がったら
そもそも、これらの車には2種類のバッテリーがあり、どちらのバッテリーが上がったかによって対応が変わってくるので注意が必要です。
駆動用バッテリーが上がった場合
このバッテリーはモーターを動かすために高電圧の電気を蓄えているので一般の方が一人で修理や整備を行うのは非常に危険です。そのため駆動用バッテリーが上がった場合はすぐにロードサービスなどに依頼をしましょう。
補機用バッテリーが上がった場合
補機用バッテリーはメーターなどの電気製品への電力供給やハイブリッドシステムを起動させるために使用されます。このバッテリーが上がってしまった場合はジャンプスターターを使用することで一般の方が一人で対応が可能です。
バッテリーが上がる原因
ここまで解説してきたように、バッテリーはガソリンやエンジンオイルなどと同じくらい、車の走行には欠かせないものです。
では、バッテリーが上がってしまうのは、いったいどのような原因があるからなのでしょうか?具体的に解説していきます。
半ドア、ライト消し忘れによる消費電力の増加
車のドアが半ドアの状態になっていると、室内灯も点いてしまうため、電力消費からバッテリー上がりの原因になってしまいます。
また同様に、夜間走行の後、ヘッドライトなどをつけたままエンジンを切ってしまい、そうした状態が長時間続いてしまうと、バッテリーに蓄電された電気が減少していき、なくなってします。
エンジンをつけずにエアコンを使用
停車中、エンジンをつけずにエアコンを使用してしまうと、蓄電されているバッテリーの電気をずっと消費していることになってしまいます。
このような状態で長時間エアコンをつけていると、バッテリー上がりの原因になってしまいます。
なお、エンジンをつけない状態では、夏などクーラーは使用できず送風となってしまいます。熱中症を起こす危険もあるため、気をつけましょう。
長期間の放置による自然放電
車を運転しなかったとしても、バッテリーは自然放電され、少しずつ電気量が減っていきます。
車を走らせている場合、蓄電量は減りながらも充電もされるため問題はありませんが、長期間車を運転しない場合、いざ久しぶりに乗ろうとするとバッテリーが上がってしまっていることもあるため気をつけましょう。
バッテリーの寿命
バッテリーの寿命により、上がってしまうことがあります。バッテリーが劣化し古くなっていると、日頃車をよく走らせ、充電を頻繁に行なっていたとしても蓄電されにくくなってしまいます。
そのため、バッテリー上がりを防ぐよう日頃からガソリンスタンドなどで状態を確認し、定期的に交換するようにしましょう。
後付け電装品による消費電力の増加
車がエンジンをかけていない状態でも、電装品が消費している電流を待機電流と呼びます。
カーオーディオやドライブレコーダーなど、後付け電装品を取り付けることによってこうした待機電流が増え、走行中は消費電力も増大してしまうので、放電や充電不足を招いてしまいます。
そして、容量も足りなくなってしまうため、バッテリー上がりを引き起こしてしまうのです。
事故等の衝撃によるバッテリー損傷
事故等の衝撃で、バッテリー内部が故障してしまう場合があります。
外部は問題ないように見えるバッテリーでも、エンジンがかからない、セルモーターが回っていない、室内灯や表示ライトが点かないなどの症状が見られる場合は、バッテリー損傷やバッテリー上がりが考えられます。
すみやかに交換するようにしましょう。
バッテリー上がりを予防する対策
日頃の運転から注意し、バッテリー上がりを未然に防ぎたいものです。では、バッテリー上がりを予防する方法として、どのようなことが考えられるのでしょうか?具体的に解説していきます。
定期的に運転する
車を運転し、エンジンを動かすことによってバッテリーは充電されます。
そのため、定期的な運転がバッテリー上がりを防いでくれます。車は運転していない状態でも、バッテリーは自然放電され、走行頻度が少なければ充電もされないため、バッテリーは上がってしまうのです。
車は実際に走行しなくても、定期的に30分ほどエンジンをかけることによって充電はされるため、このような方法でもバッテリー上がりは予防できます。
バッテリーを充電する
前述のようにバッテリーは、エンジンを動かすことによって充電されます。その他、カー用品店などで購入できるカーバッテリー充電器があれば、自分でバッテリーを充電することができます。
ただし、機種によって充電の仕方も異なるので、取扱説明書などでよく確認してから作業するようにしましょう。
定期的にバッテリーを交換する
バッテリーが上がってしまってから交換しようとすると、救援車に来てもらうか、ロードサービスの力が必要になってしまい、手間や時間、コストがかかってしまいます。
こうした負担を減らすためにも定期的にバッテリーを交換した方がよいでしょう。
今現在、バッテリーがどのような状態にあるか、ガソリンスタンド等でも無料点検してくれるため、積極的に利用するようにしましょう。
バッテリーの寿命は一般的に2~4年とされていますが、どのような道路をどのように走行するかによっても大きく変わってきます。
まとめ
バッテリー上がりはエンジンがつくか、セルモーターが回っているか、電装品が作動するかなどで確認することができます。
バッテリーが上がる原因には消費電力の増加など、様々なことが挙げられますが、一度上がると自然回復することはないため、普段から定期的に運転し充電させることや2~3年おきに交換することが重要になります。
また、実際に上がった場合の対処法としてはジャンピングスタートやジャンプスターター、バッテリーの充電・交換、ロードサービスを呼ぶなどが挙げられます。