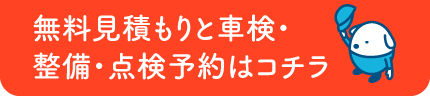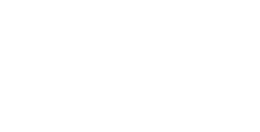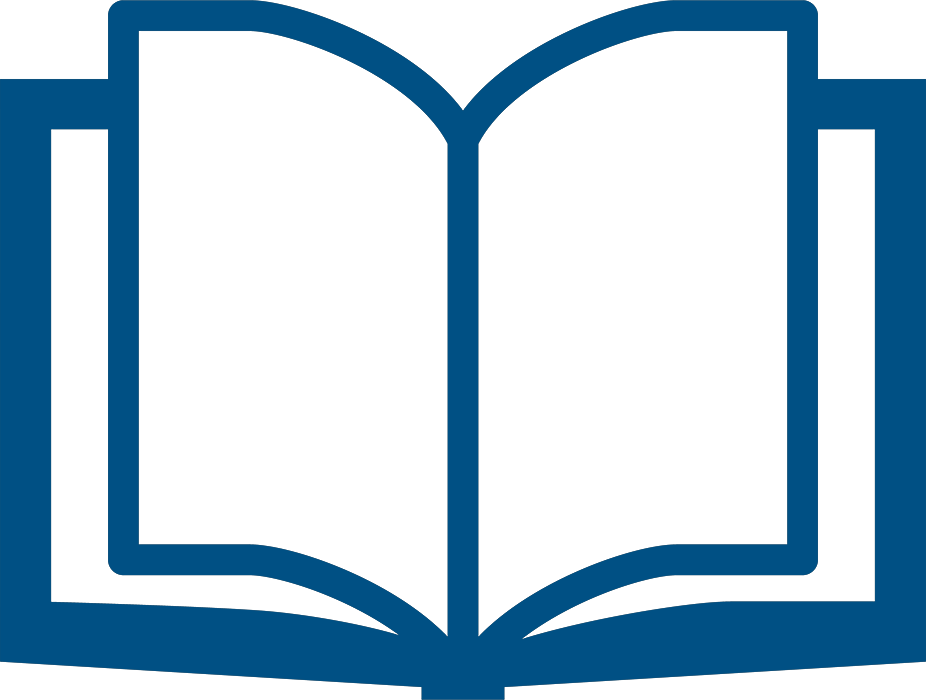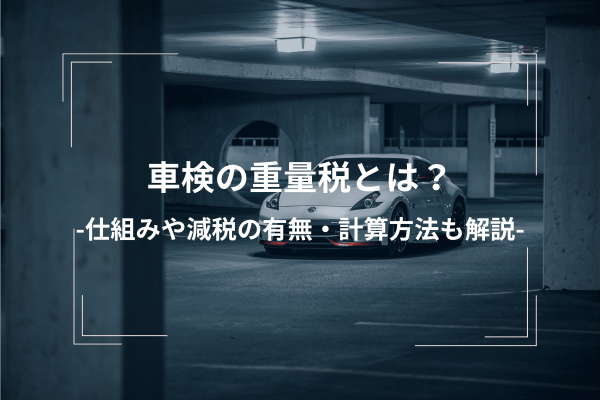
車検案内ハガキに記載されている費用のなかに重量税という項目がありますが、重量税とは一体何のために納める費用なのでしょう。
- 「重量税はどのような税金なのか?」
- 「重量税は何に使われるのか?」
- 「なぜ同じ車でありながら軽自動車の重量税はなぜ安いのか?」
このような疑問を持つ理由として、重量税が車検の諸費用のなかでも高額であるにも関わらず、税額の違いや計算方法がわからないといった点が挙げられます。
今回は、重量税は何に使われるのか?税額の違いや計算方法からわかる重量税の仕組みを解説していきます。
目次
自動車重量税とは?
重量税とは、昭和46年、自動車重量税法に基づき制定された税金です。車検証が交付される全ての車に課税され、自動車の重量によって税額は違ってきます。納税方法は、新車登録時に納税し、その後は車検毎に納税しなければなりません。徴収された重量税は、3/4が国の財源(一般道路建設費など)に1/4が市町村の一般道路の整備費などに補填されます。
納税義務者は、自動車を保有または使用している人になります。納税するのは車検時で、乗用車の場合、2年分をまとめて支払います。重量税が納税できないと、車検を更新できず、運転ができなくなります。
車検費用の内訳
車検は、重量税の他にもさまざまな費用が必要です。車検にかかる費用は、法定費用+車検基本料金+その他諸費用と大きく3つに分類されます。
- 法定費用
- 車検基本料金
- その他諸費用
それでは、車検費用の内訳について見ていきます。
法定費用
法定費用とは、どこで車検を受けても金額の変わらない費用のことです。
- 自賠責保険
自賠責保険は、自動車の使用者に加入が義務付けられている保険です。自賠責保険に未加入の自動車は、車検を受ける資格がありません。保険料は車種や契約期間で異なり、2025年度の24か月契約の例では、普通乗用車で17,650円、軽自動車で17,540円です。
※地域によって異なる場合があります。
- 検査印紙
車検を受ける際、国と陸運局や軽自動車検査協会に支払う手数料が検査印紙です。車検を受ける場所と車種によって違います。整備工場を利用した場合、普通車4ナンバーと5ナンバーは1,800円、3ナンバーは1,800円、軽自動車は1,800円となります。
重量税は、法定費用に含まれるものの一つです。税額は決まっていますが、計算方法や細かく分類されています。
車検基本料金
車検基本料金とは、24ヶ月法定点検や代行料の他に人件費なども含まれます。そのため、整備工場やディーラーなど依頼する業者によって大きく異なります。
その他諸費用
その他の諸費用とは、車検整備の際、交換や補充が必要となる部品代や別途工賃です。これらの費用によって車検代の総額が大きく変わる場合もあります。
重量税の計算方法・仕組み
重量税は、法定費用に含まれる税金ということがわかりました。しかし、自賠責保険と検査印紙のように車種や車検を受ける場所で金額がわかるものではありません。重量税の税額は、以下の4つの項目を基準に決まります。
- 車種
- 年数
- 車両重量
- エコカー減税の有無
車種
自動車は、大きく分けると2つの車種があります。
- 普通車
- 軽自動車
さらに、自家用や事業用などに分けられ、車種毎に決定します。
軽自動車は、乗用車と貨物車の区別なく一律です。また、8ナンバーは特殊用途車に分類されます。
年数
重量税は、新車登録時から13年経過すると増税対象車となり、18年経過するとさらに税額があがります。それでは、13年と18年ではどのくらい重量税の額があがるのか一覧で見ていきます。
エコカー対象外自家用乗用車の場合
自家用貨物車の場合、1年車検なので増税額は2年車検の半額となります。
車両重量
重量税の基準として車両重量があります。「自動車重量税」という名前からわかるように、重量税は、車検証に記載された車両重量で税額が定められてるのです。
重量税は0.5tから始まり、0.5t毎に区切られます。例えば、車検証に記載された車両重量が2000kgの場合「〜2.0t」に該当しますが、2001kgでは「〜2.5t」となります。マイカーの重量を車検証で確認しておきましょう。
エコカー減税対象車の免税・減税の割合と基準
最近、よく耳にする「エコカー減税」ですが、重量税にも大きく関わります。エコカー減税とは、国土交通省が定める排ガスと燃費の規定値に達した自動車に対し、自動車税と重量税が軽減される優遇措置です。国土交通省から認定を受けたエコカーには、下記の基準値が記載されたステッカーが貼られています。
上記の基準は、2025年5月1日から2026年4月30日と定められていますが、エコカー減税は延長されることもあります。
【最新版】車検の重量税一覧表
重量税は、他の車検費用に比べると細分化されて算出されているため、マイカーの税額がわかりにくいのが難点です。
それでは、軽自動車と普通車の重量税を一覧にして見ていきます。
軽自動車重量税早見表
普通車重量税早見表
軽自動車は、車両重量や車種に関わらず税額が決まっているうえ、普通車に比べると安く設定されているのが一覧を見るとわかります。
重量税計算シミュレーション
※条件等、様々な要因により計算が異なる場合がございますので、正確な金額については自動車重量税照会サービスや車検の際にスタッフにご確認ください。
国土交通省「次回自動車重量税額照会サービス」とは?
重量税が増税となるタイミングは、初年度登録から13年経過だけではなく、登録月も関わってきます。また、同じ自動車でもガソリン車とハイブリッド車で減税率が変わる可能性もあります。このような時、役に立つのが重量税を自分で調べることができるサービスです。国土交通省のホームページに掲載されているので活用すると確実なる税額がわかり便利です。
それでは、使い方を説明していきます。
- 検索したい自動車の車検証を用意する
- 国土交通省のホームページを開ける
- 「継続検査の自動車重量税額」にある「次回自動車重量税紹介サービス」をクイック
- 「照会画面へ」のボタンをクイック
- 「車体番号」「次回検査予定日」を車検証を確認しながら入力して「照会」をクイック
これで、重量税額がわかります。軽自動車も同様の方法で調べることが可能ですが、照会画面が違うので注意しましょう。
廃車するときは要注意!還付申請とは?
平成17年1月1日に自動車リサイクル法がスタートしました。同時に道路運送車両法も改正され、自動車の抹消登録関係の手続きと使用済みの自動車に関する自動車重量税の還付制度が成立しました。この制度により廃車となった自動車に一定期間の車検が残っていた場合、重量税が還付されます。
還付の手続き方法は、自動車の最終使用者がリサイクル業者に解体を依頼します。リサイクル業者から使用済みの自動車が適正に解体されたとの連絡が入った後、最寄りの陸運局または軽自動車検査協会へ行き、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請を行います。
また、一時抹消登録や車検有効期限が1ヶ月以内に切れる場合は還付申請が出来ないので、必ず窓口で抹消の仕方を聞いたり車検期日の確認を行ってから手続きをしましょう。
まとめ
今回は、重量税の仕組みや計算方法について解説してきました。重量税は、車検時に必要な法定費用に属します。税額は決まっていますが、他の法定費用とは違い、車種や車両重量、経過年数やエコカー減税も関連してくるので一見すると税額がわかりにくい費用にはなっています。
マイカーの税額が早見表などでわからない時には、国土交通省のホームページを活用しましょう。ホームページには、早見表以外にも重量税照会サービスという便利なサイトもあるので車検証さえあれば、即時に算出してくれます。