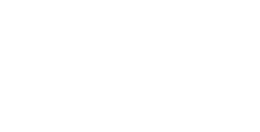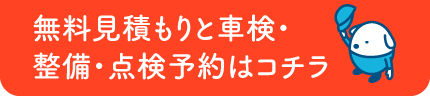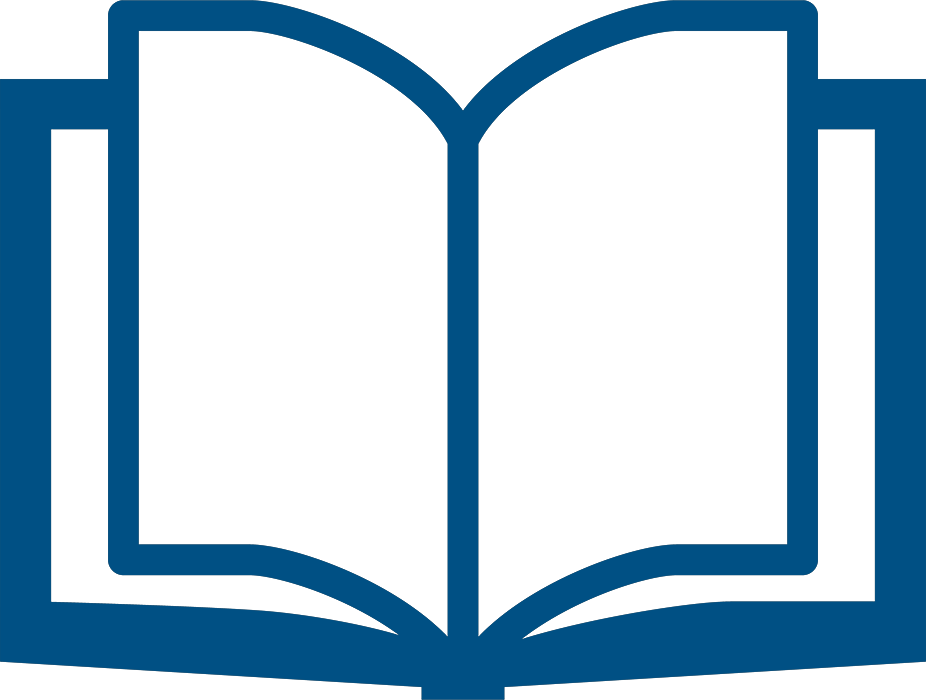自動車保険への加入を考えている場合に必ず知っておきたいのが等級についてです。
等級は全ての保険会社の任意保険で共通して適用され、保険料を決める大切な指標となっています。
等級について何となくはわかっていても、いざ事故が起きたり保険を乗り換えたりした時にどうなるのかよくわからない方も多いでしょう。
そこでこの記事では等級とは何かやどのように等級が決まるのかその仕組みについて紹介しながら、等級の引継ぎについても見ていくことにします。
目次
自動車保険の等級
まずは自動車保険の等級とは一体何なのかについて見ていきましょう。
ノンフリート等級
1人の契約者が自動車保険をかける車の数が9台以下の場合はノンフリート契約になります。
自動車保険の等級というのはノンフリート契約で適用される割引制度のようなものです。
個人で自家用車を所有する場合はほぼ全てこのノンフリート契約になるので、等級はドライバー全員に関係すると言ってもいいでしょう。
通常1等級から20等級までありそれぞれの等級に保険料の割引率が定められています。
フリート保険
1人の契約者が10台以上の車の保険に加入する場合、ノンフリートではなくフリート契約となります。
ノンフリート契約は車1台1台に別々に保険をかけるのに対し、フリート契約は契約者(会社や事業主)単位での保険契約になるのが一番大きな違いでしょう。
フリート契約には等級がなく、フリート割引率に従って保険料が割引されます。
この記事で説明する自動車保険の仕組みや決まりは、フリート契約ではなく等級があるノンフリート契約についてのものです。
自動車保険の料金が決まる仕組み
等級は自動車保険の料金を決めるうえで重要な要素になります。自動車保険が決まる要素には等級を含んで次の7つがあります。
- 保険料と免責
- 等級
- 車種や型式
- 車種と用途
- 契約者の年齢
- 新車かどうか
- 運転手限定かどうか
同じ補償内容の保険に加入するとしても上記の条件によって保険料が変わります。
また事故を起こした場合その年以降の保険料の評価に、事故係数も加わります。
等級と保険料の関係
それではいよいよ等級と保険料の関係を詳しく見ていくことにしましょう。
先ほども少し触れたように等級は1から20まであり、数字が大きくなるにつれて適用される割引率がどんどん大きくなっていきます。
各等級の割引率の参考を一覧にしました。
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 | 9等級 | 10等級 |
| 割引率 | +64% | +28% | +12% | ー2% | ー13% | ー19% | ー30% | ー40% | ー43% | ー45% |
| 等級 | 11等級 | 12等級 | 13等級 | 14等級 | 15等級 | 16等級 | 17等級 | 18等級 | 19等級 | 20等級 |
| 割引率 | ー47% | ー48% | ー49% | ー50% | ー51% | ー52% | ー53% | ー54% | ー55% | ー63% |
初めて自動車の任意保険に加入する場合等級は6からのスタートになります。
1年間事故を起こさなかったり事故があっても保険を使わなかった場合は等級が一つ上がります。
事故有係数について
無事故であれば等級が上がるのに対し、事故があり保険を使った場合は等級が3つか1つ下がることになります。
しかも6等級以上の場合事故により等級が下がった場合は、通常の割引率ではなく事故あり係数の割引率が適用されるので気をつけたいです。
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 | 9等級 | 10等級 |
| 割引率 | +64% | +28% | +12% | ー2% | ー13% | ー19% | ー20% | ー21% | ー22% | ー23% |
| 等級 | 11等級 | 12等級 | 13等級 | 14等級 | 15等級 | 16等級 | 17等級 | 18等級 | 19等級 | 20等級 |
| 割引率 | ー25% | ー27% | ー29% | ー31% | ー33% | ー36% | ー38% | ー40% | ー42% | ー44% |
事故あり係数の割引率は事故無し係数の割引率より低くなります。
13等級で3等級ダウンの事故を起こすとその後の保険料はこうなります。
| 事故の年 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 |
| 13等級 | 10等級の事故あり係数 | 11等級の事故あり係数 | 12等級の事故あり係数 | 13等級 |
事故の翌年だけでなく3年間事故あり係数の割引率が適用されるので気をつけたいです。
次に13等級で1等級ダウンの事故を起こした場合の等級の推移も見ておきましょう。
| 事故の年 | 1年後 | 2年後 |
| 13等級 | 12等級の事故あり係数 | 13等級 |
自動車保険の等級が決まる仕組み
ここではさらに詳しく自動車保険の等級が決まる仕組みを見ていきましょう。
先ほども触れたように1年経つごとに必ず上下があります。
等級の上がり方
等級が上がるのは無事故で1年の自動車保険の満期を迎え契約の継続をした時です。
事故を起こしても保険を使わなかった場合も等級が上がります。
等級の下がり方
等級が下がるのは事故を起こして保険を使った次の年です。
3等級下がり事故あり係数が3年間続く事故と1等級下がり事故あり係数が1年だけ適用される事故があるので、それぞれの特徴を見ておきましょう。
3等級ダウン事故
まず3等級ダウン事故ですが、車を運転していて起こるほとんどの事故はこちらになると考えてください。
簡単に例をいくつか紹介しておきましょう。
- 他の車との衝突し対物賠償保障を使う
- 人身事故を起こして対人賠償保障を使う
- 単独事故で車両保険を使う
- 当て逃げに合って車両保険を使う
1等級ダウン事故
対して1等級ダウンの事故は3等級ダウンのような相手がいる事故ではなく、不可抗力や犯罪それにいたずらなどで車両保険を使うケースです。
こちらもいくつか例をあげておきます。
- 駐車している間に落書きをされたり窓ガラスを割られたりした
- 飛び石や走行中に落下物が当たった
- 車の盗難にあった
- 台風や洪水にあった
1等級ダウン事故の場合はまず修理費用と翌年どれだけ保険料が上がるかを概算しましょう。
翌年以降の保険料が大きく上がる場合は保険を使わずに自分で修理した方がお得になるケースがあります。
ノーカウント事故
事故の中にも保険を使っても等級に影響せず翌年無事故の場合と同じように等級が上がる事故もあり、これをノーカウント事故と呼びます。
基本的に自分の車への損害に対してかけている特約のみの支払いが発生した場合がこれにあたります。
ノーカウント事故になる特約は保険会社によって違うのですが、代表的なものはこちらです。
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
- 無保険車傷害特約
- 弁護士費用特約
- ファミリー傷害特約
- 個人賠償責任特約
- 事故時代車費用特約
ノーカウント事故にあたる特約の補償だけが必要な場合は等級に影響しないため、遠慮なく利用するようにしたいです。
自動車保険の等級の引き継ぎ
等級は保険会社の間で引き継ぐことができるので安心してください。
それどころか等級は人と人の間でも引き継ぐこともできます。
他の保険会社に移る場合の等級の変化
等級は自動車保険を乗り換える時もそのまま引き継ぐことができます。
ただ無事故の場合満期前に乗り換えるか満期のタイミングで乗り換えるかで等級の扱いが若干変わります。
満期のタイミングで乗り換える場合は保険の空白期間が8日以上できると等級が引き継げなくなるので気をつけましょう。
- 満期前に乗り換える場合 → 乗り換え後1年間は乗り換え前の等級になる
- 満期のタイミングで乗り換える場合 → 乗り換えのタイミングで1等級上がる
そしてもし事故をした場合もその情報は等級とともに乗り換え先の保険会社に伝わります。
乗り換え先の保険会社でも規定通りきっちり等級が下がることになるので、事前に自分から伝えておいたうえで見積もりを取った方がいいでしょう。
等級の引き継ぎが可能な続柄
そして等級は親から子供へ等のように家族間で引き継ぐことも可能です。
ただ家族なら誰でも引き継げるわけではなく一定の条件が設けられています。
まず引継ぎができる対象者はこちらです。
- 主に運転する人(記名被保険者)の配偶者
- 主に運転する人(記名被保険者)の配偶者6親等以内の血族か3親等以内の姻族
そして対象者が配偶者以外の場合、主に運転する人かその配偶者と同居していることが条件となります。
子供に等級を引き継ぎたいと考えてももし親元から離れて一人暮らししている場合は引き継ぐことができません。
家族間での等級引継ぎのタイミング
親が使っていた車をそのまま子供に渡す場合は記名被保険者を子供に変更するだけで等級が引き継げます。
この場合いつでも好きな時に手続きしてください。
ただ子供が新しく車を買う場合はそうはいきません。
等級を引き継ぎ手続きの前に、車両入替の手続きをする必要があります。
親の車を親がそのまま使い続ける場合は、別に自動車保険に入りなおす必要があります。
家族間での等級引継ぎのメリット
なぜ家族観で等級を引き継ぐのかというと引き継いだ人の保険料を安くできるからです。
免許を取って間もない10代や20代は保険料が高くなるため、親の高い等級を引継ぐことで子供の保険料をおさえることができます。
ただそうすると親が新しく自動車保険に加入した場合、等級を6から始めないといけません。
といっても親の年代は子供の年代より自動車保険料が安くなる傾向がありますし、ゴールド免許の場合はさらに割引が加算されます。
一定の条件をクリアする場合親の車はセカンドカー割引が適用される可能性もあるでしょう。
親の車と子供の車2台に保険をかけると考えたとき、子供に親の等級を引き継いだ方が全体の保険料を抑えられる場合は等級を引き継ぐメリットが大きくなるでしょう。
まとめ
今回は自動車保険の等級について詳しく説明してきました。
等級は自動車保険の割引率を決めるもので、無事故だった次の年は等級が上がり事故があると反対に下がってしまいます。
自動車保険を乗り換える際には等級をそのまま引き継げますが、事故情報も同時に引き継がれます。
自動車保険料を抑えたいと考える場合、等級について知ることはとても大切です。